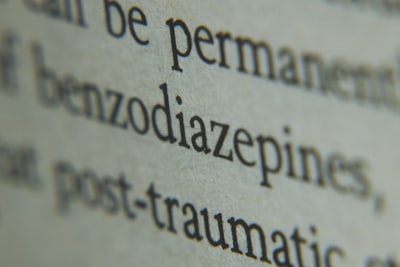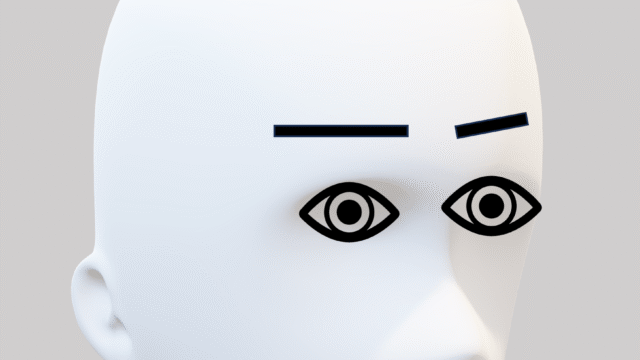中毒診療を苦手としている先生は多いのではないでしょうか。私もどちらかというと苦手です。なにせ相手が多すぎます。相手というのは患者ではなく、中毒物質です。アルコール、睡眠薬、アセトアミノフェン、炭酸リチウム、抗うつ薬、洗剤、農薬などなど。ハチや毒ヘビ、毒キノコだってあります。薬物だけではありません。水中毒や食塩過量内服の症例もあります。薬も過ぎれば毒となる。もはや何でもありです。
ベンゾジアゼピン中毒などは見慣れていますが、たまにしか診療しない中毒は毎回本を調べて半減期や致死量、代謝経路、治療などを確認しています。
今回は中毒の中でも診療する機会の多いベンゾジアゼピン中毒についてまとめます。初期対応は簡単な部類に入りますから、ぜひ対応できるようにしてください。
まず診断ですが、尿中薬物検査キットを用います。現病歴を聴取すればそれだけでも原因が推定できますが、大抵、意識障害がありますので、原因不明の意識障害に出会ったら薬物検査をするようにしてください。救急外来において、薬物中毒は常に鑑別に挙げておかないと足元をすくわれます。
今回は診断がついたところから始めます。さて、ベンゾジアゼピン中毒の患者に対してその後どう対応すべきでしょうか。
中毒診療の大原則ですが、ABCの安定化、吸収の阻害、排泄の促進、拮抗薬が初期治療において重要です。初期対応後はこれに加えて精神科の介入も検討します。原則に沿って対応していけば問題ありません。
ABCの安定化
舌根沈下はしていないでしょうか、重症症例では呼吸抑制が起きます。唾液の垂れ込みで誤嚥性肺炎を併発することもあります。Cの異常はまれですが、洞性徐脈、低血圧の症例報告があります。長時間倒れていれば低体温になっていることもあります。バイタルサインを一通りチェックしてください。
吸収の阻害
胃洗浄は昔ほど行われなくなっています。もともと安全性の高い薬なので、致死量を内服しており、かつ内服から1時間以内であれば考慮する程度です。活性炭は投与しましょう。活性炭は1g/kgです。成人であればざっくり50gぐらいだと思ってください。
排泄の促進
透析療法は有効ではなく、尿のアルカリ化も有効性は認められていません。自然と抜けてくるのを待ちましょう。
拮抗薬
ベンゾジアゼピン系薬剤に対する拮抗薬にフルマゼニル(アネキセート®)があります。0.2~0.3mgを覚醒が得られるまで繰り返し投与します。添付文書を見るとICU領域では2mgまで投与を繰り返すと書いてありますが、患者の状態により適宜増減すると続きます。2~3mg投与しても目が醒めないなら別の意識障害の原因を探したほうが良いでしょう。なお、中毒界隈では有名な話ですが、フルマゼニルの半減期は50分程度です。これはベンゾジアゼピン系薬剤の半減期よりも短いです。つまり、フルマゼニルで覚醒してもフルマゼニルの血中濃度が先に落ち、再度意識障害が起こります。フルマゼニルは診断のために用いますが治療のためには基本的用いません。フルマゼニルで目が醒めたから帰宅させるはなしです。
ベンゾジアゼピン中毒の症例に当たったら上記原則に沿って対応します。意識障害があるなら入院でしょうが、基本的には経過観察のみです。薬が抜ければ身体的には1~2泊で十分でしょう。入院後は過量内服の背景に対する介入が必要です。認知症の高齢者が誤って薬を飲みすぎたのであれば、介護者が薬の管理をするようにします。自傷行為であれば精神科の介入を検討してください。
↓私が愛用している中毒のバイブルです。おすすめです。
| 臨床中毒学 第2版 [ 上條 吉人 ]価格:14300円 (2025/3/23 08:13時点) 感想(0件) |