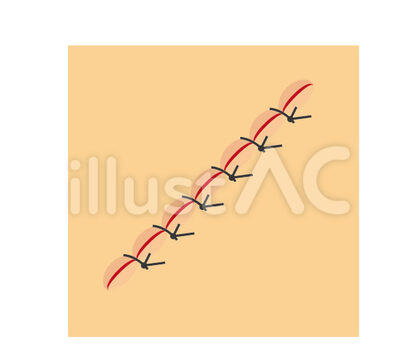「ついでに〇〇も調べてもらえませんか。」
救急外来で、あるいは病棟で時たま聞かれるリクエストです。特に高齢の方が入院したときに、認知症の検査とか癌の検査などリクエストされます。
結論から言うと、できません。
せっかく病院に来たんだからという気持ちはわかります。しかし、救急外来では必要最低限な検査と治療しかしません。もし、せっかくだからCTやMRIで色々調べて欲しいという要求が通るなら、もはやそれは人間ドックです。救急の場で行うことではありません。
入院した患者家族から「市の検診でひっかかって、今度こちらの病院で胃カメラをする予定でした。この入院中に胃カメラもお願いします。」と言われたこともあります。
気持ちはわかります。この病院で胃カメラ予定だったわけですし。しかし、これもできません。入院した原因疾患とは無関係の検査を行うこと、これもやはり人間ドックと同じです。
多くの急性期病院ではDPC(包括評価方式)と呼ばれる支払制度が導入されています。病名に対して医療保険の保険者から支払われる金額が包括的に決まっているのです。例えば、(数字は適当ですが)脳梗塞で入院すると病院に支払われる金額が100万円と決まっており、その中で検査や治療を行います。入院が長引いたり、余計な検査が増えたりすれば、病院に残るお金は減っていきます。
(すごくざっくりした説明です。本当はもっと複雑です。)
なんだ、お金の問題かとは思わないでください。今回の入院と関係ない検査を“ついでに”行うことは他の患者の不利益につながります。緊急性のない検査を割り込みでいれることになるので、他の患者の迷惑です。業務が圧迫され、急患発生時の対応に遅れが出たりしかねません。検査が増え、入院期間が延びれば病床確保に支障がでます。
割り込みで検査や治療を行うのは原則として医学的に緊急性が認められる場合のみです。
繰り返しますが、“人間ドックではない”のです。そして、今回あなたが入院したのは別の理由があり、まずはその問題を早急に解決すべきなのです。
仕事が忙しくて時間が取れないとか、通院が大変とか、色々なお気持ちがあると思います。
社会資本としての救急医療を維持していくために、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。